LNG燃転(CO2削減)に関係する費用としては、イニシャル費、ランニング費、労務費の3つのモノサシで検討するのが良いでしょう。
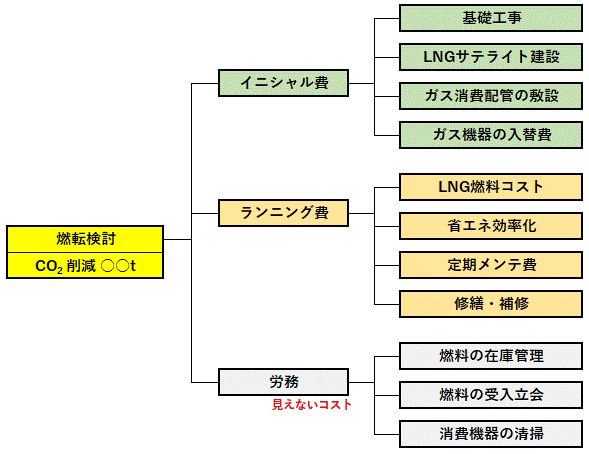
- イニシャル費は、上図のほか建設工事に入る前の撤去・整備費用も考慮しましょう
- ランニング費は、設備運転に必要なユーティリティ(LNG代、電気代、水道代、窒素やエアー代)や、年1回の法定検査の受検費、将来の設備修繕費を想定しておくのが良いです
- 労務費は数値化されにくい部分ですが、手間が掛かる方向になるのか / 楽になるのか をあらかじめ把握しておきましょう。例えば重油の場合はガス消費機器の内部が汚れるため定期清掃が必要だが、LNG(ガス)はクリーンなので清掃の手間からは解放されます。しかしLNGは受入時に立会(拘束)がある・・・といった一長一短比較が大事ですね。
イニシャル費(最初に掛かる費用)
大別すると4つの要素になります。
基礎工事
LNGサテライトの基礎工事費用です。高圧ガス保安法の耐震基準に準拠して設計施工されます。大地震でもタンク倒壊を防ぐだけの基礎強度が求められます。そのため過去の大震災においても、LNGサテライトのタンク倒壊事例はこれまでありません。
工場の立地によって地盤はさまざまなので、まずはボーリング調査(試掘)を行い基礎設計の条件を定めます。地盤が柔らかい場合は、地盤改良工事や杭工事が必要となります(高いです!)。
LNGサテライト建設
基礎工事が完成したのち、LNG貯槽、気化器(蒸発器)、減圧弁などからなるガス供給設備が建設されます。基礎工事を除くサテライトの上物(うわもの)工事を専門に行っている会社は、業界では 4~5 社程度あります。各社とも一長一短、得意不得意があります。原則的にはLNG販社(ユーザーにとっての窓口会社)がタッグを組んでいる会社を連れてくるため、ユーザーがサテライト建設会社を選ぶことは少ないでしょう。これが「設備とLNGが一体の提案」のケースです。
中には、LNGの購入と設備の購入を切り離して検討が進むケースもあります。この場合は、ユーザーが上述の 4~5 社からLNGサテライトの見積を取得して比較検討を行う必要があります。
メリット :購入商流を簡素化できるため建設費用は大きく低減できる
デメリット:建設中や設備運開後のサービスが行き届かないものになる可能性あり(建設する専門会社は中小規模のため)
こちらも一長一短です。筆者の感覚ですと、ユーザー側がある程度の規模の工場で、工務や設備管理部門がしっかりしている場合は、(LNG販社を通さずに)直接 購入しても運用に耐えうると思います。そうでない工場の場合は、LNG販社を通しての設備購入が良いかと思います。高くなる分は将来の安心代ですね。
4~5社のサテライト建設の専門会社については、各社とても特徴がありますのでまた機会をみて記事を書きます。
ガス消費配管
LNGサテライトとガス機器までの間をつなぐ連絡配管のことです。ガス配管が細くて済むのか太いのか、総長が短いのか長いのかで費用は大きく変わるため、LNGサテライトがガス機器から離れすぎない場所に建設することが経済設計のポイントです。
ガス機器
ボイラーや炉のバーナーや発電機などのガス消費機器のことです。既存の設備が老朽化している場合は入替更新を行います。バーナーを調整(改造)することでLNG化に対応できる場合は、設備の新規更新よりも安く済みます。
一般的には工場のガス機器が止まる(生産が停止する)ことはG.W.や盆や年末年始の長期休暇の時しかないため、LNG燃転プロジェクトはココから逆算して全体工期が定められます。
ランニング費用(運用開始後に掛かる費用)
LNG燃料コスト
もっとも大事なファクターです。いかに良い価格で購入(契約)できるかが肝です。
- 商流に窓口会社を挟まない(余計な口銭の発生を回避)
- より多くLNG輸入している会社を選ぶ(海外からより多く仕入れている会社の方が、良い価格でユーザーへ提示できる)
- より多くのLNG燃転実績がある会社を選ぶ(有事の際の対応力に大きな差がある:トラブルシュート経験数)
- 出荷基地が近い会社を選ぶ(配送運賃を安く抑える/大雪の際の配送ストップのリスクを極力低減)
- 配送ローリーを沢山所有している会社を選ぶ
とはいえLNG購入時の選択肢は(工場の立地エリアによっては)最初からとても限られているため、他の燃料を購入する際の交渉のようには進みません。上手に価格交渉を行い、契約期間(ロックされる期間)は長期になりすぎないように注意しましょう。
省エネ化
LNG燃転では古い燃料消費機器から最新型のLNGガス機器へ入替されるため、燃焼効率の向上が期待できます。燃焼ロスが無くなり燃料使用量の削減(省エネ)につながります。
定期メンテ費
1年に1回、法定検査を受ける費用です。検査会社は万一のトラブル時に備えて駆け付け対応が可能な、なるべく近くの会社を選ぶのが望ましいでしょう。15年程度の長期使用する設備のため、毎回違う会社が検査を行うよりも同じ会社に依頼するのが良いと思われます。
修繕・補修
サテライト、ガス消費機器ともに長期使用に伴い経年劣化が起こります。大きなトラブルが発生する前に機器の交換を行っていく必要があります。年に1回の定期メンテの際に異常の初期兆候を確認し、予防保全に繋げることが大切です。設備を15年使用すると想定した場合、折り返しの8~10年目あたりで一定のメンテ修繕を行うのがポイントです。特に電気計装系はプラントの心臓部ですので、きちんと予算を積んで置きましょう。
労務(見えないコスト)
燃料の在庫管理
LNGの場合は、ローリーからの フルドロップ が基本となります。LNGサテライトの貯槽はこの事情を考慮して大きさを決める必要があります。小さめのタンク(40~50kl)では、14~15 t のLNGを積んだローリーでフルドロップする場合、貯槽の残量を空近くまで減らさねばなりません。
液面管理の担当者は、常にガス切れを起こさないようにしつつもピンポイントなタイミングで毎回ローリーを呼ぶ必要があります。世の中には幾つかこのような設備が存在しますが、とてもストレス値の高い運用となってしまいます。
現在では遠隔監視のシステムが組まれており、LNG販社とユーザーの双方で液面を管理して次回以降のローリー配送計画を組むようになっています。上述のような小さい貯槽のケースだと、事前に定めたローリー配車計画に頻繁な変更が生じることになり、配送会社側にとっても運用負荷が高まりあまり良いことがありません。
長期(15年~20年)の間、このような燃料在庫管理を行うことになるため、少し余裕のある貯槽サイズ選定をしておくことがお勧めです。
燃料の受入立会
LNGの受入にはおよそ1.5時間ほど掛かり、受入担当者(ユーザー)の立会が求められます。人手が足りないので立会(拘束)されるのが厳しい…なんて声もよく聞かれます。ユーザーからすると、LNG燃転に伴ってあらたに発生する労務として映ると思います。
消費機器の清掃
一方、重油ユーザーがガス化を行った場は消費機器の清掃の頻度・労力はかなり減ります。この部分は労務コストのカットにつながる良い話です。
-scaled.jpg)
-300x225.jpg)

コメント